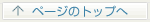2025年2月号
- 宇宙政策委員会の宇宙輸送小委員会、第8回会合を開催
- イーロンマスク、可能な限り速やかなISSの軌道離脱を要求
- FCCの前長官、アメリカの大手ローファームに入所
- 内閣府、「人工衛星等との衝突防止に係るガイドライン」を制定
- [コラム①]Italian Space Law Sparks Controversy Over Musk's Influence
- [コラム②]Kevin Holden Platt, Crashing Space Station In 2027 Will Trigger Backlash Across ISS Allies
- [コラム③]Richard M. Carson, Remote sensing and the international law of space
- [コラム④]Michael Garetto-Balmer, Reaping space’s decline? Why to choose the durability of due regard over the debris of military devastation
- [コラム⑤]清水亘、山田智希「宇宙法務】宇宙活動法の見直しに関する中間とりまとめの公表 その1 ―見直しの全体像・再使用型ロケット等に関する新たなルール―」
- [コラム⑥]清水亘、山田智希「【宇宙法務】宇宙活動法の見直しに関する中間とりまとめの公表 その2 ―再突入・有人飛行に関する新たなルール・その他の論点―」
- [コラム⑦]風木淳「宇宙政策をめぐる最近の動向」
- [お勧めの文献①]Navinya N. Kamble, Towards Ensuring Peace in Space (Notion Press, 2025).
- [お勧めの文献②]青木節子ほか編『宇宙法の位相』(信山社、2025年).
- [お勧めの文献③]Anthi Koskina , Manolis Plionis, Greek Space Law ―Collaborating with a Growing Space-faring Country (Springer, 2025).
- [お勧めの文献④]Charles Berebon, “Indigenous Rights and the Night Sky: Reconciling Satellite Mega-Constellations with Indigenous Astronomical Traditions,” Traditions. Advances in Law, Pedagogy, and Multidisciplinary Humanities, Vol. 3(1), p. 84.
- [お勧めの文献⑤]Sirio Zolea, Comparative Space Law―The Space Frontier from a Private Law Perspective (Brill, 2025).
宇宙政策委員会の宇宙輸送小委員会、第8回会合を開催
https://www8.cao.go.jp/space/comittee/05-yuso/yuso-dai8/gijisidai.html
[SPLメモ] 2025年2月6日、内閣府の宇宙政策委員会に設置された宇宙輸送小委員会は第8回会合を開催した。同会合では現在調整中の宇宙活動法改正に関する議論の状況の共有と、宇宙産業の主要分野における「宇宙スキル標準」案に関する検討が行われた。同スキル標準は宇宙産業に関わるための「必須スキル」ではなく、あくまでスキル向上のための「指針」である旨が強調されている。
イーロンマスク、可能な限り速やかなISSの軌道離脱を要求
https://spacenews.com/musk-calls-for-deorbiting-iss-as-soon-as-possible/
[SPLメモ] 2025年2月20日、スペースX社のCEOであるイーロンマスク氏は自らのSNSアカウントにおいてISSの速やかな軌道離脱を訴える投稿を行った。同投稿の意図は必ずしも明らかではないが、ISSは現状、その耐用年数の問題を抱えている。他方で、アメリカが計画中の商用宇宙ステーションは2030年までの完成も疑問視されており、ISS体制からのシームレスな移行につき課題が残っている。
FCCの前長官、アメリカの大手ローファームに入所
https://spacenews.com/former-fcc-space-bureau-chief-joins-law-firm/
[SPLメモ] 宇宙開発における法律家、法律事務所の役割は拡大している。日本でも宇宙開発に関する国内法や国内制度の整備における弁護士の活躍や、スペースベンチャーの関係者を集めた宇宙法セミナーの開催など、法律家は様々な形で宇宙開発に関わっている。
内閣府「人工衛星等との衝突防止に係るガイドライン」を制定
https://www8.cao.go.jp/space/application/space_activity/documents/ca_guideline.pdf
[SPLメモ] 2025年2月27日、内閣府は「人工衛星等との衝突防止に係るガイドライン」を制定した。同ガイドラインは昨年の3月に案が提示され、国民の意見募集等を経て公開に至ったものである。ガイドラインはあくまで「考え方や具体的な方策等の一例を示すもの」であることが強調されており、情報共有やリスクの把握・管理といった事項が記載されている。
[コラム①]Italian Space Law Sparks Controversy Over Musk's Influence
https://evrimagaci.org/tpg/italian-space-law-sparks-controversy-over-musks-influence-234576
[SPLメモ] 宇宙開発におけるイタリアの存在感は近年向上しており、スペースX社のような国際的なスペースベンチャーからの注目も集めている。他方で、海外の宇宙産業の参入はイタリアという国家の利益と企業の利益の調整という新たな問題を発生させるものでもある。宇宙活動の商業化、国際化に伴う問題に対してイタリアの立法府がどのようなかじ取りを行うのか、今後の展開に注目すべきだろう。
[コラム②]Kevin Holden Platt, Crashing Space Station In 2027 Will Trigger Backlash Across ISS Allies
[SPLメモ] ISSは人類の宇宙開発を支えてきた前哨基地であったが、宇宙物体の宿命である耐用年数の問題から逃れることはできない。その幕引きについては純法学的観点(ISS IGA、宇宙諸条約、その他の国際法との適合性)だけでなく関連国家の宇宙戦略との兼ね合いから考える必要がある。
[コラム③]Richard M. Carson, Remote sensing and the international law of space
https://www.thespacereview.com/article/4941/1
[SPLメモ] 宇宙活動の商業化はリモートセンシング分野において大きな産業の構造転換をもたらし、今や多くの国家が商用リモートセンシングを利用している。リモートセンシングに関する既存の国際的な枠組みとしては宇宙諸条約やリモートセンシング原則が挙げられるが、その十分性については慎重に検討し、必要な改善策を模索していく必要があるだろう。本コラムはそのようなリモートセンシングに関連する法制度の現代的な分析を簡潔に行っているものである。
[コラム④]Michael Garetto-Balmer, Reaping space’s decline? Why to choose the durability of due regard over the debris of military devastation
https://spacenews.com/trekking-into-the-stars-why-due-regard-provides-us-a-new-hope/
[SPLメモ] 宇宙条約はその9条1文において他国の対応する利益に対し「妥当な考慮」を払う宇宙活動国の義務を課している。この条文はかつてそれほど存在感のあるものとは考えられてこなかったが、主にデブリ問題の深刻化に伴いその重要性が認識されるようになり、現在では規範内容の明確化を含む同条の活用方法の模索が盛んに行われている。
[コラム⑤]清水亘、山田智希「宇宙法務】宇宙活動法の見直しに関する中間とりまとめの公表 その1 ―見直しの全体像・再使用型ロケット等に関する新たなルール―」
https://www.amt-law.com/insights/newsletters/newsletter_20250205001_ja_001/
[SPLメモ] 現在日本は内閣府を中心として宇宙活動法の改正を見据えた議論が行われている。本資料は先月に公開された中間とりまとめの内容を解説するものとなっている。
[コラム⑥]清水亘、山田智希「【宇宙法務】宇宙活動法の見直しに関する中間とりまとめの公表 その2 ―再突入・有人飛行に関する新たなルール・その他の論点―」
https://www.amt-law.com/insights/newsletters/newsletter_20250207001_ja_001/
[SPLメモ] (同上)
[コラム⑦]風木淳「宇宙政策をめぐる最近の動向」
https://www.jihyo.co.jp/topics/saizennsen-cao202501kazeki01.html
[SPLメモ] 宇宙開発戦略推進事務局長である風木 淳氏が宇宙政策における主要な6ポイントについて解説。2024年3月された宇宙戦略基金の説明(月刊『時評』2025年1月号掲載)。
[お勧めの文献①]Navinya N. Kamble, Towards Ensuring Peace in Space (Notion Press, 2025).
https://notionpress.com/my/read/towards-ensuring-peace-in-space
[SPLメモ] 宇宙法の起草における政治的背景も検討し、宇宙空間の平和利用を確保するはずだった宇宙諸条約を包括的に分析。
[お勧めの文献②]青木節子ほか編『宇宙法の位相』(信山社、2025年).
[SPLメモ] 最先端宇宙技術に関する法的課題を宇宙法研究者および実務家が多角的に考察。
[お勧めの文献③]Anthi Koskina , Manolis Plionis, Greek Space Law ―Collaborating with a Growing Space-faring Country (Springer, 2025).
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-72813-6
[SPLメモ] ギリシャの国内宇宙法に関する文献。
[お勧めの文献④]Charles Berebon, “Indigenous Rights and the Night Sky: Reconciling Satellite Mega-Constellations with Indigenous Astronomical Traditions,” Traditions. Advances in Law, Pedagogy, and Multidisciplinary Humanities, Vol. 3(1), p. 84.
https://jurnal.fs.umi.ac.id/index.php/alpamet/article/view/795
[SPLメモ] 衛星メガコンステレーションと先住民の天文学的伝統に関する論文。国連宇宙空間平和利用委員会(UNCOPUOS)の科学技術小委員会では「暗くて静かな空」に関するWGが設置され、議論が始まったばかりのテーマ。
[お勧めの文献⑤]Sirio Zolea, Comparative Space Law―The Space Frontier from a Private Law Perspective (Brill, 2025).
https://brill.com/display/title/71693
[SPLメモ] 宇宙法シリーズの最新版。本人格、財産権、損害賠償に関する国内私法と国際宇宙法の関連性に着目する文献。