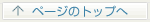2025年3月号
- アメリカ、ウクライナへの衛星画像支援を停止
- 宇宙法模擬裁判大会が開催
- アメリカ、ウクライナへの衛星画像支援を再開
- 内閣府宇宙政策委員会、「宇宙活動法の見直しの基本的方向性中間とりまとめ」を了承
- 運輸総合研究所、「弾道飛行等による大陸間輸送事業に関する 法的諸問題に関する研究会 報告書」を公表
- 第3回宇宙交通管理に関する関係府省等タスクフォース大臣会合の開催
- [コラム①]"The Challenge of Corporate Sovereignty in Outer Space"
- [コラム②]"Autonomy Has Outpaced International Space Law"
- [お勧めの文献①]Matthew Gillett, Katja Grunfeld and Iva Ramu? Cvetkovi?, Lex Ad Astra Non-State Actor Accountability for Space Pollution (BRILL, 2025).
- [お勧めの文献②]Matylda Berus, “European Space Puzzle: Evaluation of the Space-Related Institutional Players in Europe,” Air and Space Law, Vol. 50(2) (2025), p.191.
- [お勧めの文献③]竹内悠『商業宇宙活動と国際法』(信山社、2025年)
アメリカ、ウクライナへの衛星画像支援を停止
https://spacenews.com/us-halts-satellite-imagery-support-to-ukraine-in-major-policy-shift/
[SPLメモ] 2025年3月7日、トランプ政権はウクライナによる商用衛星画像プラットフォームへのアクセスを停止する旨の発表を行った。同プラットフォームによるサービス提供はロシア・ウクライナ戦争におけるウクライナの優位性に貢献してきたものであり、停戦に向けたウクライナ側への圧力の一環と思われる。
宇宙法模擬裁判大会が開催
https://www.sljsc.org/information/
[SPLメモ] 2025年3月8日から9日にかけて第20回宇宙法模擬裁判大会 日本大会が開催された。同大会は初の英語ラウンドが導入され、日本語大会、英語大会共に早稲田大学が優勝した。早稲田大学は翌月インドで開催されるIISL Manfred Lachs Space Law Moot Court Competitionのアジア太平洋地域予選にも出場する予定である。
アメリカ、ウクライナへの衛星画像支援を再開
https://spacenews.com/u-s-restores-satellite-imagery-support-to-ukraine-amid-ceasefire-tensions/
[SPLメモ] 2025年3月18日、トランプ政権はウクライナに対する商用衛星画像プラットフォームサービスの提供を再開した。同サービスは3月7日に停止が発表されたものである。
内閣府宇宙政策委員会、「宇宙活動法の見直しの基本的方向性中間とりまとめ」を了承
https://www8.cao.go.jp/space/comittee/kaisai.html
[SPLメモ] 2025年3月25日、内閣府の宇宙政策委員会は先月公開された「宇宙活動法の見直しの基本的方向性中間とりまとめ」を了承した。宇宙活動法は日本の宇宙活動の実質的な骨組みとなる法であり、その改正には注目が集まっている。
運輸総合研究所、「弾道飛行等による大陸間輸送事業に関する 法的諸問題に関する研究会 報告書」を公表
https://www.jttri.or.jp/report2025.pdf
[SPLメモ] 2025年3月25日、一般財団法人 運輸総合研究所は「弾道飛行等による大陸間輸送事業に関する 法的諸問題に関する研究会 報告書」を公表した。同報告書は超音速旅客機やサブオービタル飛行技術の発展によって宇宙空間と捉え得る空間を通過する輸送技術がもたらす法的問題につき、国際法・国内法双方の観点から検討を加えたものとなっている。
第3回宇宙交通管理に関する関係府省等タスクフォース大臣会合の開催
https://www8.cao.go.jp/space/taskforce/debris/kaisai.html
[SPLメモ] 依然として人類の宇宙活動の脅威であり続けるデブリ問題や軌道上サービスに関する技術の発展など、宇宙交通管理に関する状況は変化し続けている。第3回の会合では先月公開された「??衛星等との衝突防?に係るガイドライン」を念頭に、宇宙交通管理に関する状況の確認と関係省庁の取り組みの確認が行われた。
[コラム①] Aaditya Vikram Sharma, "Starlink and International Law: The Challenge of Corporate Sovereignty in Outer Space"
[SPLメモ] 米民間企業SpaceX社が展開しているメガコン「Starlink」が国際法に及ぼす法的課題を検討するとして、宇宙ビジネスを展開する企業-New Space-間の国際協力体制を模索する。現状では宇宙条約第6条に基づき、国家が自国民の活動に対して継続的監督をするのみであり、企業間の協力の重要性を指摘する文献として貴重。
[コラム②]Matthew Ormsbee, "Autonomy Has Outpaced International Space Law"
https://warontherocks.com/2025/03/autonomy-has-outpaced-international-space-law/
[SPLメモ] AIを搭載した人工衛星がメガコンや衛星通信システムに使われ始めたことを機に、宇宙条約第9条の適用可能性を模索する。衛星がIoT化している現在、AIに適用される国際法の文脈で宇宙法を再考する視点もあるとさらに良い。
[お勧めの文献①] Matthew Gillett, Katja Grunfeld and Iva Ramu? Cvetkovi?, Lex Ad Astra Non-State Actor Accountability for Space Pollution (BRILL, 2025).
https://brill.com/display/title/69509
[SPLメモ] New Spaceによる環境損害として「space pollution」を検討。宇宙条約第6条を超えた検討としては上記コラム①と同テーマ。
[お勧めの文献②]Matylda Berus, “European Space Puzzle: Evaluation of the Space-Related Institutional Players in Europe,” Air and Space Law, Vol. 50(2) (2025), p.191.
https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Air+and+Space+Law/50.2/AILA2025013
[SPLメモ] 複雑化するEU内の宇宙プレイヤーを機関ごとに整理し、各宇宙法政策を包括的に分析する文献としては最新のもの。
[お勧めの文献③]竹内悠『商業宇宙活動と国際法』(信山社、2025年)
[SPLメモ] 国際宇宙法が有する「事後統制機能」および「事後統制機能」に着目し、今日の商業宇宙活動に対する法システムの態様を分析する文献。